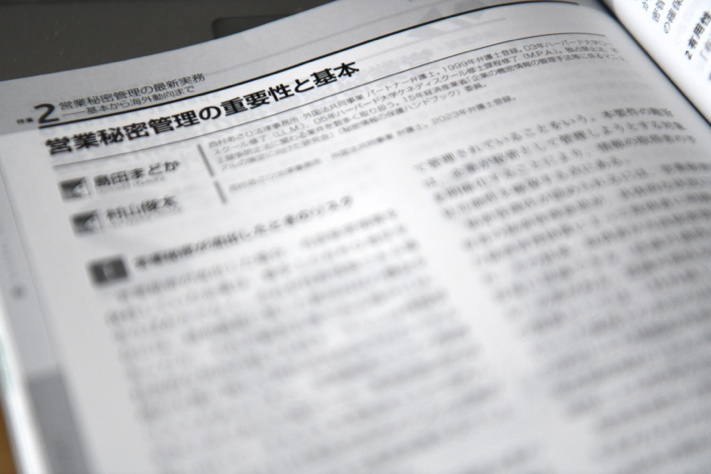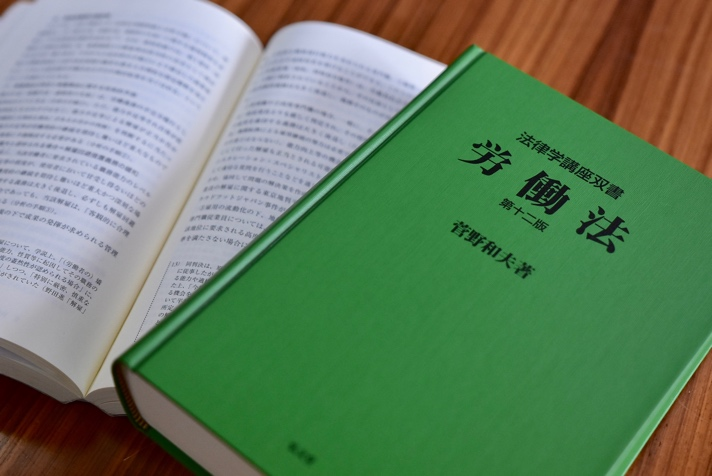第72回は、任天堂ほか事件【京都地裁令6.2.27判決】です。
本件では、労働者派遣のうち「紹介予定派遣」について、派遣労働者と派遣先との労働契約の成否が問題となりました。
1 事案の概要
原告のXさんは、派遣会社であるA社に雇用され、「紹介予定派遣」として、被告Y社で就労していました。
Xさんは、Y社の一次面接および二次面接を受け、A社から、Y社の内定が決まったとの連絡を受けました。その後、XさんはA社との間で、派遣先をY社とする労働契約を締結し、Y社での就労を開始しました。XさんとA社との労働契約の契約期間は3か月となっており、3か月後には1度、労働契約の更新がなされました。
派遣期間が6か月間経過する頃、Y社はXさんがY社従業員との円滑な協力体制の構築に至らないことを理由に、Xさんを直接雇用せず、紹介予定派遣を終了しました。
そこで、Xさんは、Y社とは直接の労働契約が成立しているとして、Y社に対して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め訴訟を提起しました。
なお、裁判において、Xさんは、Y社が紹介予定派遣を終了させた理由である「Y社従業員との円滑な協力体制の構築に至らないこと」について、Y社従業員からのパワーハラスメントがあったとして損害賠償請求もしました。
2 派遣先との直接の労働契約成立の根拠
Xさんは、契約の形式上は、派遣会社であるA社と労働契約を締結しており、Y社には労働者派遣として就労していたに過ぎませんでした。
それにもかかわらず、XさんがY社との直接の労働契約が成立したと主張するのは、Xさんにとっては、本来の雇用主である派遣会社のA社ではなく、Y社がXさんの面接、採用決定を行なっており、これは、労働者派遣の枠組みを超えるもので、Xさんと派遣会社A社との派遣労働契約は無効であり、XさんとY社との間に労働契約が成立すると主張しました。
3 裁判所の判断
Xさんの主張は、採用決定に派遣先が関与することは、労働者派遣の枠組みを超えて違法な労働者供給に該当するため、労働者派遣契約は無効ということを前提としており、この前提は、通常の労働者派遣においては当てはまるものの、果たして、紹介予定派遣についても同様に解することができるかが問題となりました。
紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣労働者及び派遣先に、職業紹介を行うものをいい、当該職業紹介により、労働者派遣終了前に、労働者と派遣先との雇用が約されるものをいいます(労働者派遣法2条4号)。
労働者派遣においては、派遣先が、労働者を特定することを目的とする行為(特定行為)をしないように努めなければならないとされているところ、紹介予定派遣については、職業紹介を伴うことから、このような派遣労働者を特定する行為も許容されています(労働者派遣法26条6項)。紹介予定派遣において特定行為を許容することとした法改正(平成15年法律第82号)の趣旨は、事前面接ができずに内定に至らない直接雇用の阻害要因を失くし、派遣労働者が派遣先に直接雇用されることを推進することにありました。
このような立法過程に鑑み、本件のXさんに対する面接及び内定に関する一連の手続は、紹介予定派遣に許容されている特定行為といえるから、Xさんと派遣会社A社との派遣労働契約を無効とするような事情には当たらないとしました。
一方で、Y社従業員からの、Xさんに対するパワーハラスメントについては、Xさんに対し、一方的に定例ミーティングの中止及び廃止等をする行為があり、不法行為に該当するパワーハラスメントであると認められました。これに伴い、Y社に対しても使用者責任が一部認められました。
パワーハラスメントについて損害賠償請求は認められましたが、パワーハラスメントがあったとしても、上記A社とXさんとの労働派遣契約の成否ひいてはY社とXさんとの労働契約の成否には影響を与えず、Y社とXさんとの労働契約が成立しているとはいえないとの判断がなされました。
4 おわりに
いかがでしたでしょうか。今回は、労働者派遣のうち紹介予定派遣に関する裁判例を紹介させていただきました。
この裁判例を通して、紹介予定派遣の場合、特定行為が許容されるため、派遣先が面接や内定の手続に関与しても、違法な労働者派遣には該当しないということがわかります。
今後は、直接雇用の推進のため紹介予定派遣の導入がますます増えていくことが予想されます。労働者派遣を採用するにあたり法的なリスク等を懸念されている方は、ぜひ一度弁護士までご相談いただけますと幸いです。

弁護士 髙木 陽平(たかぎ ようへい)
札幌弁護士会所属。
2022年弁護士登録。2022年PLAZA総合法律事務所入所。北海道出身。