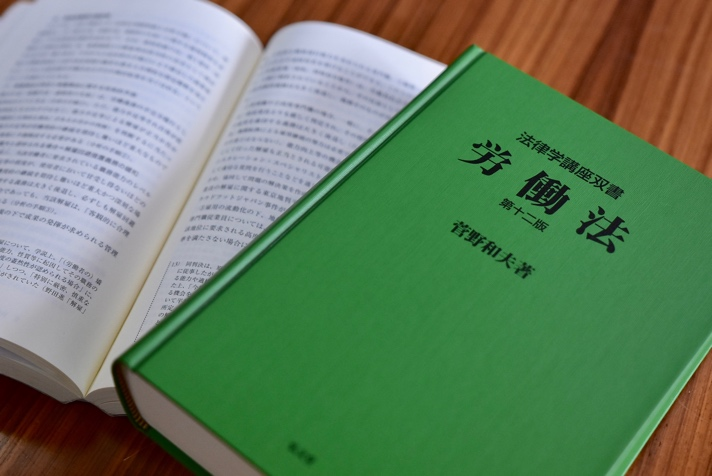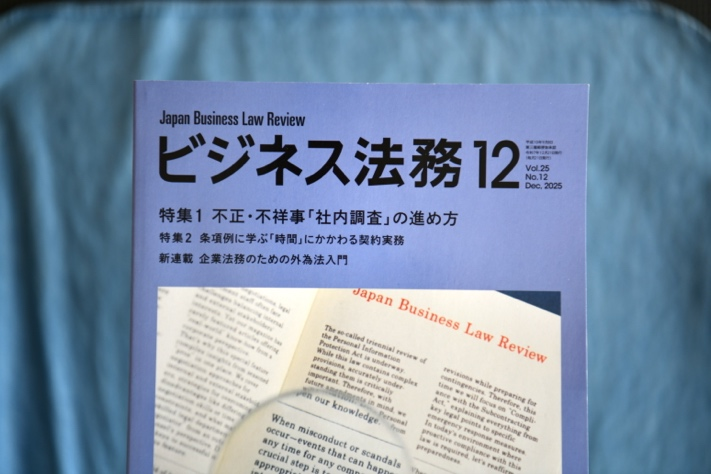第81回は、ナルシマ事件【東京地裁令和3年10月14日判決 労働判例1320号70頁】です。
本件では、外国人労働者らに対する寮費控除の適法性が争われました。
1 事案の概要
Xさんは、Y社に勤務をしていたフィリピン国籍の外国人でした。XさんはY社に対して未払い賃金の支払いを求めて訴訟提起をしましたが、その訴訟において、Xさんは、Y社が寮費としてXさんの給与額から毎月6万円を引いていたことは、Xさんの同意なく行われた違法なものであると主張して争いました。
2 賃金全額払いの原則
労働基準法第24条1項本文には、以下の規定があります。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
この規定の趣旨は、使用者が賃金の一部の支払いを留保して労働者の足留めを図ることを防止するとともに、賃金を労働者に確実に受領させその経済生活の安定を確保することにあるとされています。
この規定との関係で、使用者が社宅費用などを支払い給与額から相殺することは禁止されるのではないかが問題になります。
本判決は、他の裁判例と同様、以下のように控除(相殺)の適法性についての判断基準を示し、本件において相殺をすることは違法であると判示しました。
3 本判決の概要
①労働基準法24条第1項本文が定める賃金全額払の原則は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものである。
したがって、労働者がその自由な意思に基づき賃金からの控除に同意したと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合に限り、同意を得て行った控除は本規定に反しないと解するのが相当である。
②本件の雇用契約書においては、「月給料6万円とする。」、「給料と会社の立替費用の合計が毎月の給料となる。合計18万円となる。」、「月額18万円。所得税、社会保険料の他に、寮費として6万円を控除する。」と記載があり、雇用契約書上、一応は、6万円の寮費控除に言及があり、Xは同雇用契約書に署名を行っている。
③しかしながら、その記載は日本語表記のみであり、証拠関係からすると、通訳人によるXへの説明は行われていなかった。
④また、Y社が寮費に含まれると主張している各費目(アパート代、水道光熱費等)についての記載は、雇用契約書上も説明されていない。
⑤以上の事実関係からすると、本件においては、雇用契約書にXの署名があるという一事をもって、Xがその内容を真に理解したうえで自由に基づいて合意したものとは認められない。
⑥したがって、Y社は、Xに対し、寮費合計108万円の返還義務を負う。
4 おわりに
今回もお目通しをいただき、ありがとうございました。
顧問先の皆様におかれましても、給与の前借を求める従業員や、不祥事を起こした従業員との関係で、給与から控除する方法によって返還を行う旨の合意書を作成しておくことは、よくあるケースだと思います。本稿を踏まえて、今一度、合意書作成のプロセスを見直していただけましたら幸いです。

弁護士 白石 義拓(しらいし よしひろ)
第二東京弁護士会所属。
2022年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。栃木県出身。