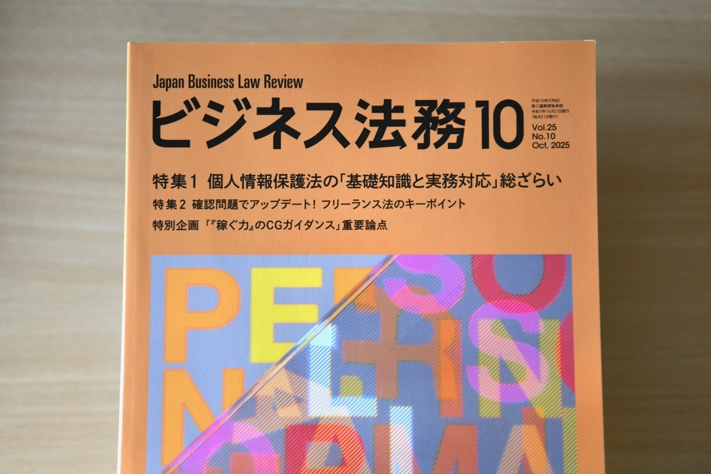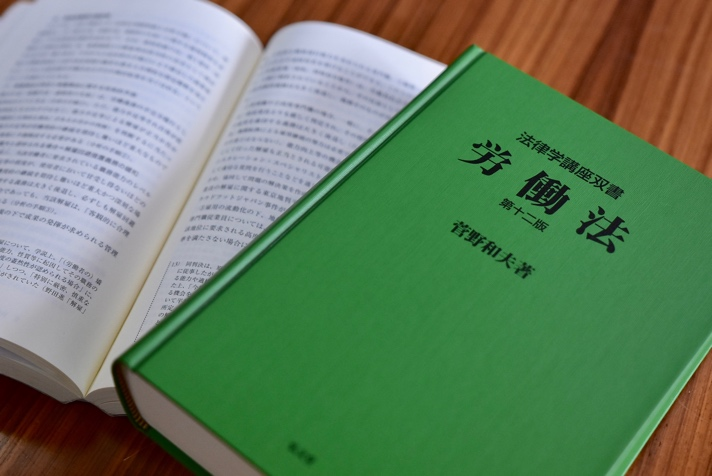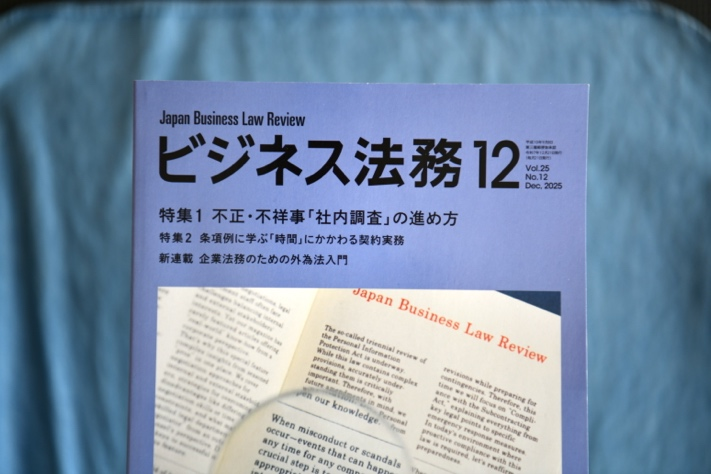『ビジネス法務』2025年10月号の「特集2」は「確認問題でアップデート!フリーランス法のキーポイント」です。その中に「偽装フリーランス問題」(執筆:大西ひとみ弁護士)があります。留意すべき点が解説されています。
- Ⅰ フリーランス法と労働法の適用関係
- Ⅱ 「労働者」該当性
- 1「労働者」該当性の判断基準
- 2実務上の対応
- 3偽装請負との関係
<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>
1 はじめに
本稿では、フリーランス法と労働法の適用関係、労働者該当性について解説されています。
2 フリーランス法と労働法の適用関係
2024年11月1日、フリーランス法(正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行されました。
もっとも、フリーランス法と労働法は、どちらか一方のみが適用される関係にあります。すなわち、業務委託契約であればフリーランス法が適用され、雇用契約であれば労働法が適用されます。そして、契約の性質は、形式(契約のタイトルなど)ではなく、実態から判断されます。
3 労働者性の判断基準
労働基準法上の「労働者」(同法9条)に該当するか否かは、「使用従属性」があるかによって判断されています。この「使用従属性」は、①「指揮監督下の労働」(労働が他人の指揮監督下において行われているか)、②「報酬の労務対償性」(報酬が「指揮監督下の労働」の対価として支払われているか否か)、の2つの基準で判断されます。
そして、①については、(a)仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無、(b)業務遂行上の指揮監督の有無、(c)拘束性の有無、という3つの基準によって判断され、(d)代替性の有無という要素も指揮監督関係の判断を補強すると考えられております。①②で判断が困難な場合は、事業者性の有無や、専属性の程度を補強要素として考慮するとされております。
それぞれの要素の具体的な考え方については、本稿90頁の図表をご覧ください。
4 近時の裁判例
近時の裁判例で、フリーランスである個人が実態としては「労働者」に該当すると判断されたものとして、大阪地判令和5年4月21日労判1310号107頁(ファーストシンク事件)があります。
本裁判例では、タレントである個人が、マネジメント会社と専属マネジメント契約を締結していたという事案において、タレントは会社の指示どおりに業務を遂行しなければ、違約金を支払うことになるとの意識のもとで仕事を遂行していたと認定され、仕事の依頼に対する諾否の自由がなかったと判断されています。そして、その他の事情も考慮した上で、タレントは「労働者」に該当すると判断されました。
5 おわりに
今回もお目通しをいただき、ありがとうございました。
新法が成立したということで、フリーランスの就業環境等に関して、今後は実務上も対応の必要が生じてくることと存じます。今月号のビジネス法務では、「フリーランス法のキーポイント」と題して特集が組まれており、本稿をはじめとして実務上のポイントが解説されておりますので、ぜひお目通しになることをおすすめいたします。

弁護士 小川 頌平(おがわ しょうへい)
札幌弁護士会所属。
2025年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。北海道出身。

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)