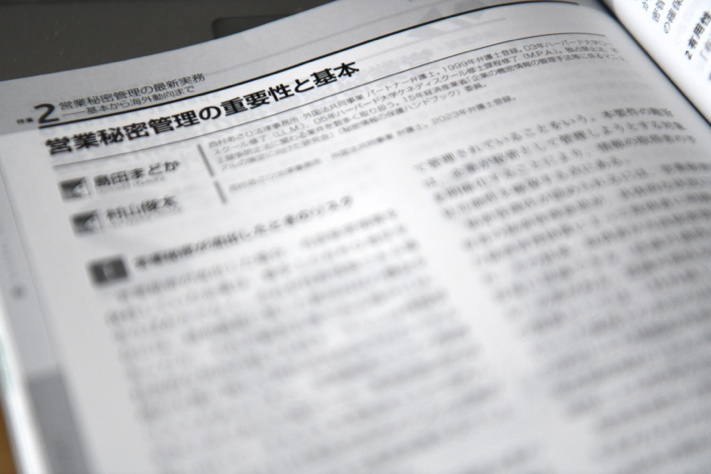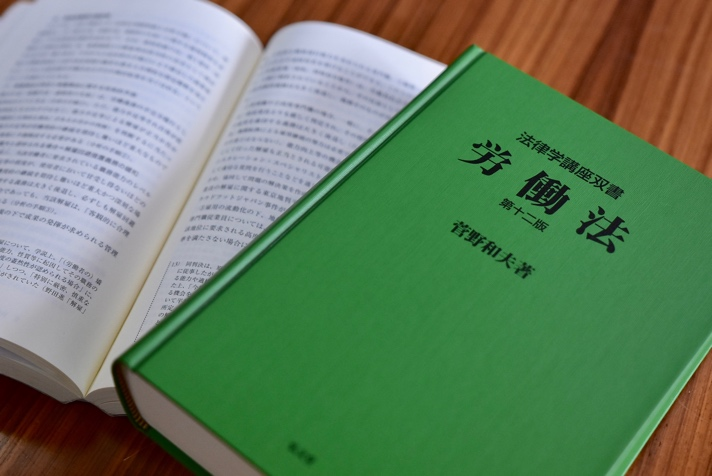第79回は、学校法人松山大学事件【松山地裁令和5年12月20日判決 労働判例1320号5頁】です。
本件では、裁量労働制に関する就業規則変更の有効性が争われました。
1 事案の概要
Xさんらは、松山大学を運営する学校法人(以下「Y法人」といいます。)で教授職に就いていました。
Y法人では、平成31年に、専門業務型裁量労働制に関する労使協定(以下「本件労使協定」といいます。)が締結されましたが、その際に行われた「労働者の過半数代表者」の選定手続きに瑕疵があるとして、Xさんらは、Y法人に対して、本件労使協定の無効を主張して、未払い残業代の請求を求めました。
2 専門業務型裁量労働制の制定経緯
労働基準法制定(昭和22年)当初、国家は、工場労働者などの集団的・画一的に働く労働者を主に念頭に置いて、法定労働時間制や時間外労働制などの画一的な規制により対応していました。
しかし、戦後復興とともに労働の専門性・多様性が高まるようになり、労働の量(労働時間の長さ)に着目した従来型の画一的な規制では対応できない専門労働者が増加するようになりました。
このような社会変化を受けて、昭和62年に実労働時間数にかかわらず労使協定で定められた時間だけ労働したものとみなす裁量労働のみなし制が導入され、平成10年には、「専門業務型裁量労働制」と呼称されるようになりました。
3 専門業務型裁量労働制の有効性
当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない時は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結する必要があります(労基法38条の3第1項)。
この労使協定が締結されていなかった場合には、就業規則に定められている専門業務型裁量労働制に関するみなし規制は無効となります(「詳解労働法」水町勇一郎「第2版」731頁)。
4 本判決の概要
本判決は、形式的には「労働者の過半数を代表するものとの書面による協定」が存在した本件においても、本協定を無効と判断しました。
①Y法人の主張:Y法人規定には、労働者の過半数代表者の選出選挙においては、「選挙に投票しなかった場合は有効投票とみなす」旨の規定が存在している。
したがって、実投票で過半数を取得することはできていないが、実投票しなかった労働者のみなし有効投票も考慮すると、本協定については、労働者の過半数の同意を取得できている。
②裁判所の判断:本選挙投票における有権者は493名であるところ、そのうち信任投票をしたのは124票であり、本協定を締結した代表者Zを指示していたのは有権者全体のわずか25%にすぎない。
労基法38条の3第1項の法意に鑑みるならば、過半数代表者の選出手続きは、労働者の過半数が当該候補者(代表者)の選出を支持していることが明確になる民主的なものである必要があり、「実投票をしなかった労働者について有効票を投じたものとみなす」旨の規定は、労働者全体の総意を汲むことのできる民主的な規定とは言えない。
したがって、本件労使協定を締結した代表者は、労働者の過半数が民主的に選定した「過半数代表者」ではないため、代表者Zが締結した本件労使協定は無効である。
5 おわりに
今回もお目通しいただき、ありがとうございました。
本稿でご紹介した「過半数代表者」の選定は、三六協定の締結場面でも多々問題になるものです。三六協定締結場面での「過半数代表者」との関係でも同様に判断される(代表者選定の民主制を欠いた場合は無効と判断される)可能性が十分にありますので、本稿をきっかけとして「過半数代表者」の選定過程について今一度ご確認いただけましたら幸いです。

弁護士 白石 義拓(しらいし よしひろ)
第二東京弁護士会所属。
2022年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。栃木県出身。