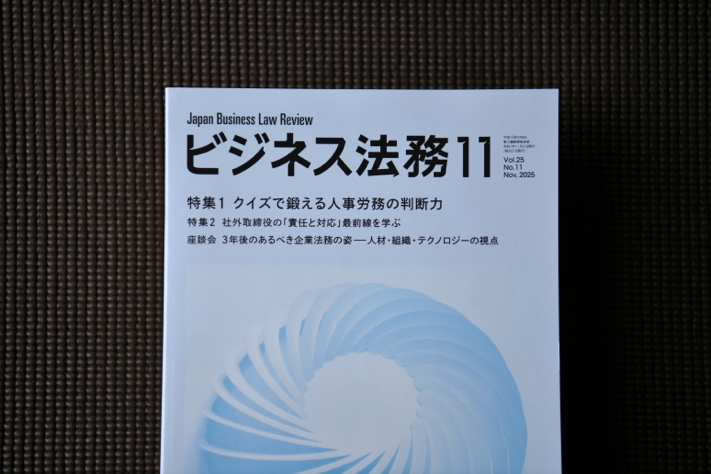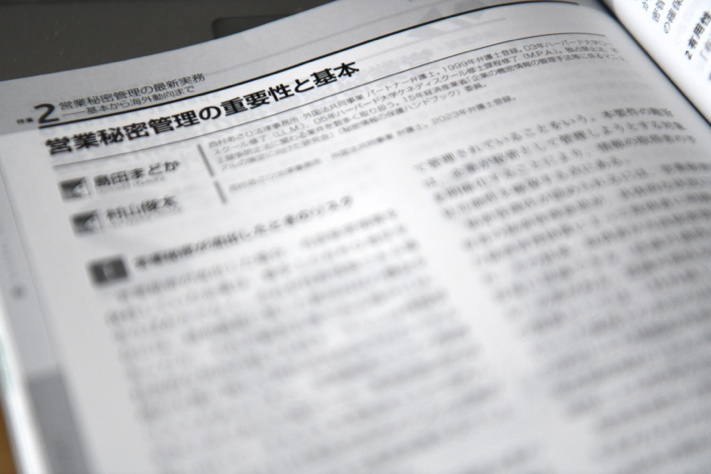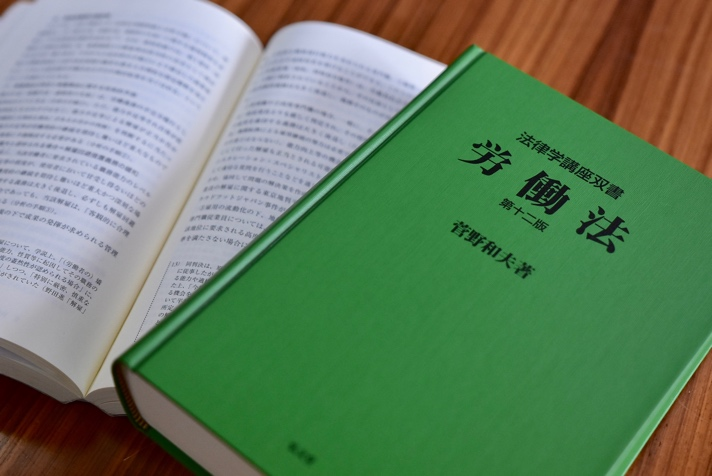『ビジネス法務』2025年11月号の「特集1」は「法務担当者のためのクイズで鍛える人事労務の判断力」です。その中に「配転・降格・出向」(執筆:藤原宇基弁護士/市川一樹弁護士)があります。この3つの点に関して、法務部門が押さえるべき重要なポイントが解説されています。
- 1−1 配転命令の有効性の判断枠組み
- 1−2 職種限定の合意
- 1−3 キャリアに関する利益
- 2−1 降格の意義
- 2−2 降格に伴う賃金減額の有効性
- 3−1 出向の意義
- 3−2 出向元の安全配慮義務
<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>
1 はじめに
本記事では、配転・降格・出向に関する企業の人事権行使について解説されています。
2 配転について
配転とは、従業員の配置変更のうち、職務内容や勤務場所が相当長期に渡って変更されるものをいいます。
配転命令が有効であるためには、①就業規則等に配転命令に関する根拠があること、②配転命令の業務上の必要性、労働者が受ける不利益等に照らして権利濫用に当たらないことが必要となります。
3 職種限定契約
就業規則等に配転命令に関する根拠がある場合であっても、職務内容を限定する特別の合意(職種限定契約)が存在する場合は、使用者の配転命令権はその範囲に限定されます。
そして、この職種限定契約は、雇用契約書上、職種限定である旨が明記されていなくても、職務内容の専門性や、当該専門職の採用ルート(通常の採用ルートとは分けて募集されている等)の事情によっては、黙示の職種限定合意が認定される可能性もあるので注意が必要です。
4 おわりに
今回もお目通しをいただき、ありがとうございました。
顧問先の企業様からは、日々、人事労務に関するご相談をいただいているところであり、多くの企業様が頭を悩ませている分野であるものと存じます。本記事では、役職毎の賃金基準が具体的に定められていなかったため降格処分に伴う基本給減額が無効とされた事例や、出向元が出向先で生じた出向者の自殺について使用者としての安全配慮義務を負うと判断された事例などについても解説されていますので、ぜひ一度お目通しいただければと思います。

弁護士 白石 義拓(しらいし よしひろ)
第二東京弁護士会所属。
2022年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。栃木県出身。

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)