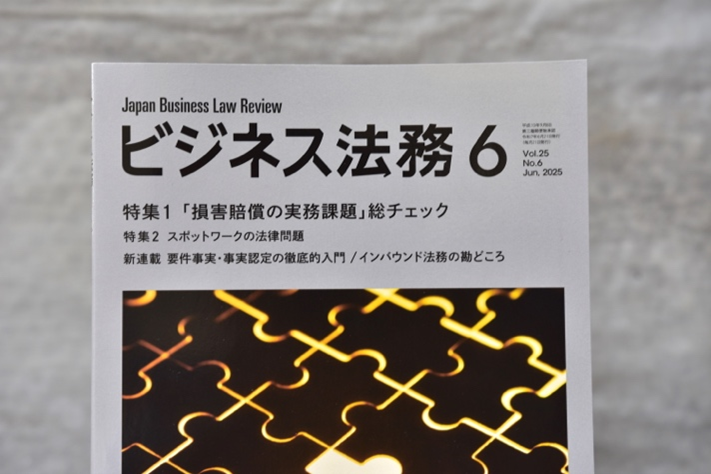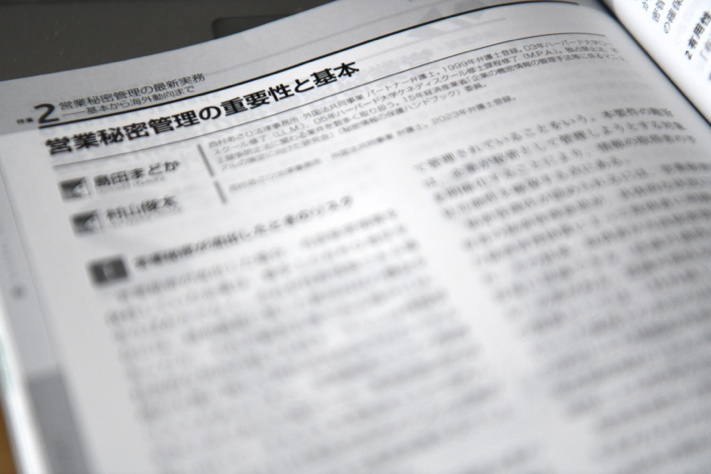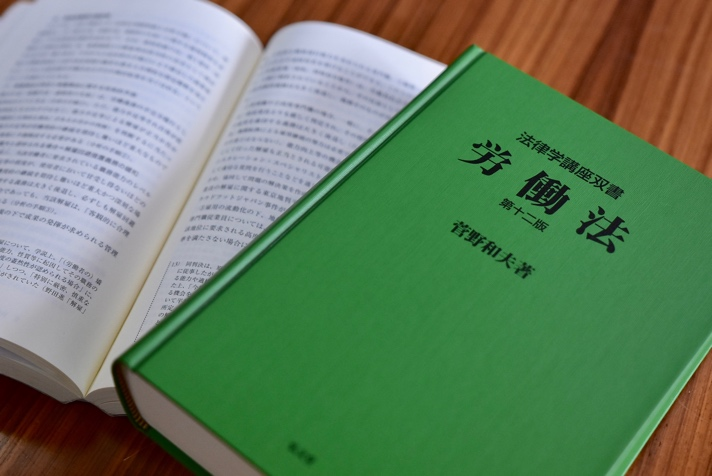『ビジネス法務』2025年6月号の「実務解説」は「『令和6年改正育児・介護休業法』の留意点」(執筆:東志穂弁護士・宮島弁護士)です。政省令をふまえた全体像について、実務上の留意点をあたらめて振り返り、解説しています。
- Ⅰ 令和6年改正育児・介護休業法の概要
- Ⅱ 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
- 1子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
- 2労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮等
- 3所定外労働の制限の対象拡大およびテレワークの努力義務
- 4子の看護休暇の見直し
- Ⅲ 育児介護休暇等の取得状況の公表義務の拡大
- Ⅳ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化
- 1介護離職防止のための個別の周知・意向確認
- 2介護に直面する前の早い段階での両立支援制度等に関する情報提供
- 3介護休業および介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境の整備の措置
- Ⅴ そのほか実務上の留意点
<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>
1 はじめに
本記事では、令和7年4月1日より順次施行されている令和6年改正育児・介護休業法(以下、「令和6年改正育介法」といいます。)についての実務上の留意点について解説されています。
2 令和6年改正育介法の要点
令和6年改正育介法の要点は、主に、①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、②育児介護休業等の取得状況の公表義務の拡大、③介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の3点です。
具体的には、①について、3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付けることや所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を「3歳になるまでの子」から「小学校就学前の子」を養育する労働者に拡大すること等が挙げられます。②について、育児休業等の取得状況の公表義務の対象を常時雇用する労働者数「1000人超」の事業主から「300人超」の事業主まで拡大すること等が挙げられます。③について、介護離職防止のための個別の周知・意向確認等の義務付けや介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供、介護のためのテレワーク等の導入の努力義務化等が挙げられます。
3 実務上の留意点
次に、実務上の留意点について、例えば、①の「柔軟な働き方を実現するための措置」について、事業主は、a.始業時刻等の変更、b.テレワーク等の導入、c.保育施設の設置運営等、d.養育両立支援休暇(年に10日以上、時間単位で取得可能)、e.短時間勤務制度の導入の中から2つ以上の措置を選択して講じる必要があります。また、③の「介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供」について、情報提供の時期については、労働者が40歳に達する日の属する年度または労働者が40歳に達した日の翌日から1年間であり、情報提供事項については、介護休業、介護両立支援制度の内容、当該制度の申出先、介護休業給付に関する内容等の情報の提供が求められます。
4 おわりに
本記事では、令和6年改正育介法の各改正点について、実務上講じるべき対応が詳しく説明されています。この機会に是非ご一読ください。

弁護士 小熊 克暢(おぐま かつのぶ)
札幌弁護士会所属。
2020年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。北海道出身。

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)