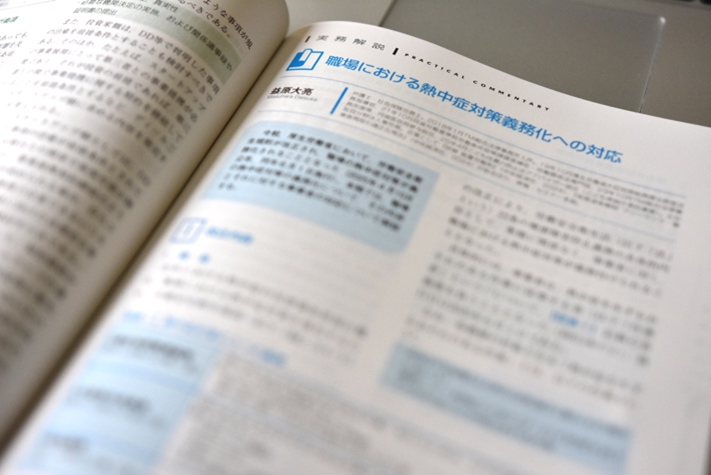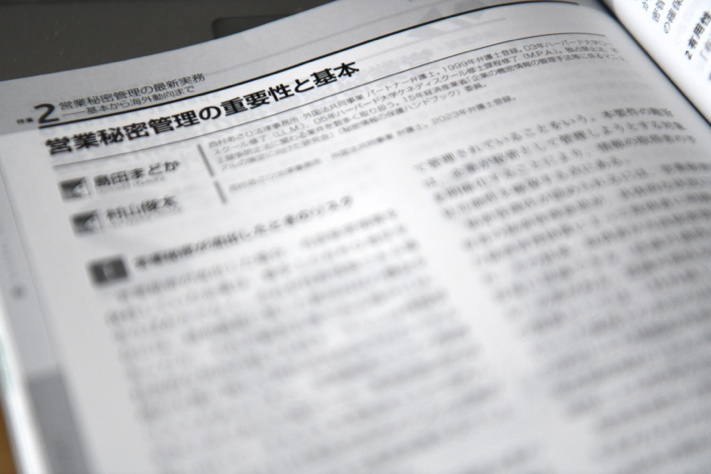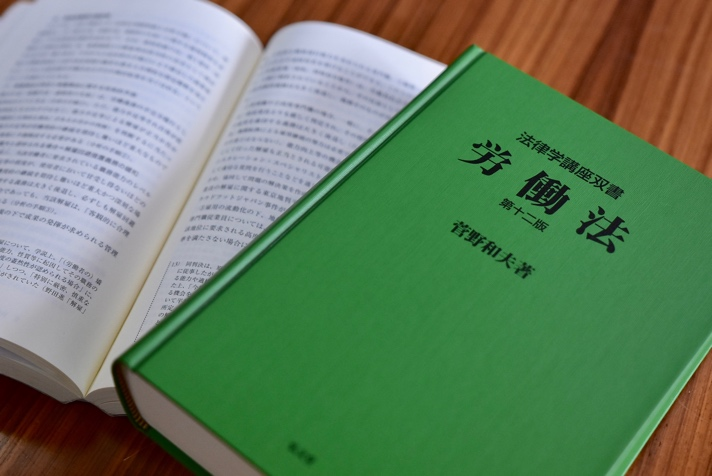『ビジネス法務』2025年8月号の「実務解説」は「職場における熱中症対策義務化への対応」(執筆:益原大亮護士)です。2025年、厚生労働省において労働安全衛生規則が改正され、職場の熱中症対策が義務化されることになりました。本稿では、その内容と事業者の対応について解説されています。
- Ⅰ 改正内容
- 1概要
- 2報告体制整備義務の内容
- 3手順等作成義務の内容
- 4報告体制整備と手順等作成の実施時期
- 5報告体制と手順等の周知義務
- 6罰則等
- Ⅱ 改正対応
- 1影響ある業種
- 2具体的な対応内容
<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>
1 はじめに
本稿では、労働安全衛生規則の改正に伴い、令和7年6月1日から施行・義務化されている『事業者の熱中症対策』について解説されています(元執筆者:益原大亮弁護士)。
2 対象作業:「熱中症を生ずるおそれのある作業」
事業者は、「熱中症を生ずるおそれのある作業」(規則612条の2)について熱中症対策を講じる必要があります。具体的には、①WBGT(暑さ指数)が28度以上または気温31度以上の場所において、②連続して1時間以上または4時間を超えて行われる作業が対象になっています。
3 事業者の義務①:報告体制整備義務
「熱中症を生ずるおそれのある作業」が行われている間、熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症の疑いがある作業者を見つけた者が、会社の責任者に随時報告できる体制を確保することが必要となります。
例)
・責任者等による作業場の巡回
・バディ制の採用(2人以上の作業者が作業中に互いの状況を確認)
・作業者と責任者間での定期連絡の実施
4 事業者の義務②:手順等作成業務
作業者が熱中症になった場合の対応手順を定めておくことが必要となります。
例)
・作業からの離脱
・身体の冷却
・必要に応じて医師の診察・処置を受けさせること
5 事業者の義務③:周知義務
事業者は、上記の2つの内容について、「熱中症を生ずるおそれのある作業」が行われる前に周知しておく必要があります。
例)
・朝礼での周知
・社内掲示板への掲示
・メールや社内イントラネットでの周知
※口頭での周知(作業者への分かりやすさを意識した伝達方法)と、メール等での周知(周知の事実を証拠として残しておくため伝達方法)を組み合わせることが望ましいです。
6 おわりに
今回もお目通しをいただき、ありがとうございました。
熱中症対策は、建設業・製造業・運送業・警備業などの業種において、特に対策が求められることが多いと思いますが、本改正では業種の限定がなく、「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う事業者様であれば、全事業者様が対象となりますので、本稿をきっかけとして、ぜひ一度ご確認をいただけたらと存じます。

弁護士 白石 義拓(しらいし よしひろ)
第二東京弁護士会所属。
2022年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。栃木県出身。

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)