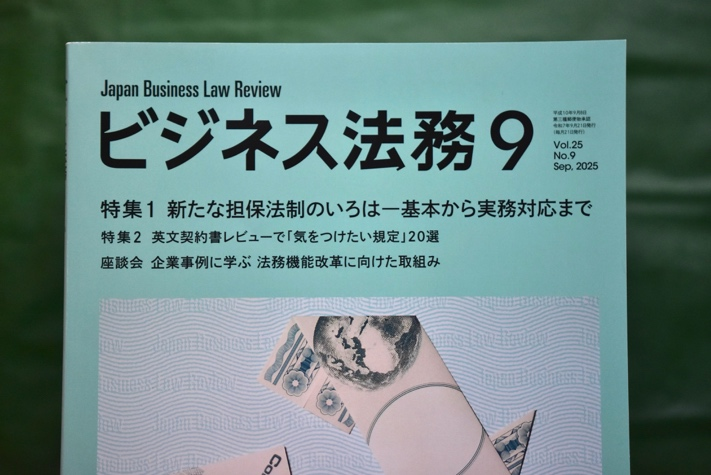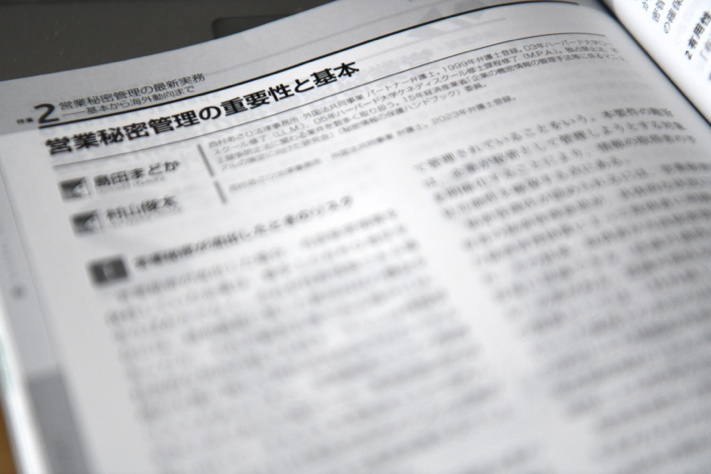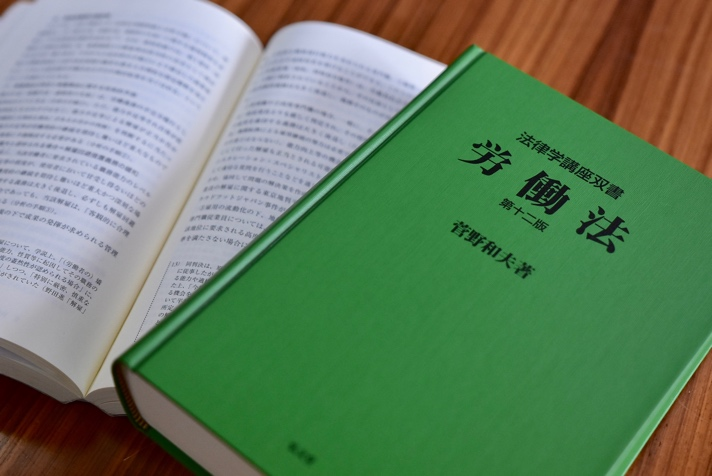『ビジネス法務』2025年9月号の「特集1」は「新たな担保法制のいろは」です。その中で、法制化の主要ポイントとして「所有権留保」が取り上げられています。(執筆:髙井章光弁護士)です。今回、新たに法律によってその内容が規定されました。この内容について、解説されています。
- Ⅰ 譲渡担保新法に規定された所有権留保
- Ⅱ 対抗要件
- 1狭義の所有権留保の場合
- 2拡大された所有権留保の場合
- Ⅲ 動産譲渡担保権の規定の準用
- Ⅳ 民事再生等の申立てを理由とする解除特約の無効
<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>
1 はじめに
本稿では、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保新法)における所有権留保の概要について解説されています(元執筆者:髙井章光弁護士)。
2 所有権留保とは
所有権留保は、これまで法律によって規定されていませんでしたが、今回新たに法律によって内容が規定されることになりました。本稿ではまず、所有権留保の定義が説明されています。
新法での所有権留保は2つの場合があります。正確な定義は本文に譲りますが、一つは、動産の売買契約において、代金の支払いを分割払いや一定期間後の支払いとしたケースで、先に目的物を買主に渡していた場合には、当該動産の上に売主は売買代金を被担保債権として留保所有権という担保権を有します(「狭義の所有権留保」)。
もう一つは、自動車割賦販売のようなケースで、購入者に代わって信販会社が代金の一括支払いをしたうえで、購入者が信販会社に対して、購入代金のほか手数料・金利などを分割して支払うこととされている場合には、弁済期間中は信販会社が購入代金の償還請求権、手数料などの債権を被担保債権として、自動車に対して留保所有権を有します(「拡大された所有権留保」)。
3 対抗要件
所有権留保の対抗要件(第三者に権利を主張するための要件)として、動産の権利の得喪・変更のために登記・登録が必要な場合には登記・登録、それ以外は引渡しが必要となりました(109条1項)。もっとも、「狭義の所有権留保」においては、売買代金支払債務のみを担保する場合、「拡大された所有権留保」においては償還債務のみを担保とする場合には、引渡しがなくても第三者に対抗することができるものとされています(同条2項)。
4 動産譲渡担保権の規定の準用
所有者留保の実行方法は、これまでは売買契約を解除し、目的物の返還を求める方法しかありませんでした。しかし新法では、帰属精算方式(目的物の所有権を取得してその評価額をもって残債務の弁済に充てる方法)、処分精算方式(目的物を第三者に売却して代金を残債務の充当に宛てる方法)によるほか、強制執行によることも可能となりました。
5 民事再生等の申し立てを理由とする解除特約の無効
「狭義の所有権留保」に関して、民事再生手続や会社更生手続の申立て等の事由が発生した際に、所有権留保契約を解除する旨の特約(倒産解除特約)は、無効であることが明記されました(110条)。
6 おわりに
今回もお目通しをいただき、ありがとうございました。
新法が成立したということで、譲渡担保や所有権留保に関して、今後は実務上も対応の必要が生じてくることと思われます。今月号のビジネス法務では、「新たな担保法制のいろは」と題して特集が組まれており、本稿をはじめとして基本から実務対応までの解説がございますので、ぜひお目通しいただくことをおすすめいたします。

弁護士 小川 頌平(おがわ しょうへい)
札幌弁護士会所属。
2025年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。北海道出身。

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)