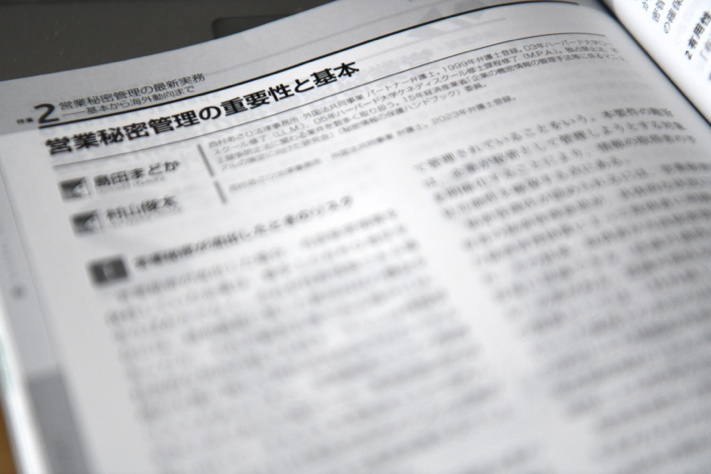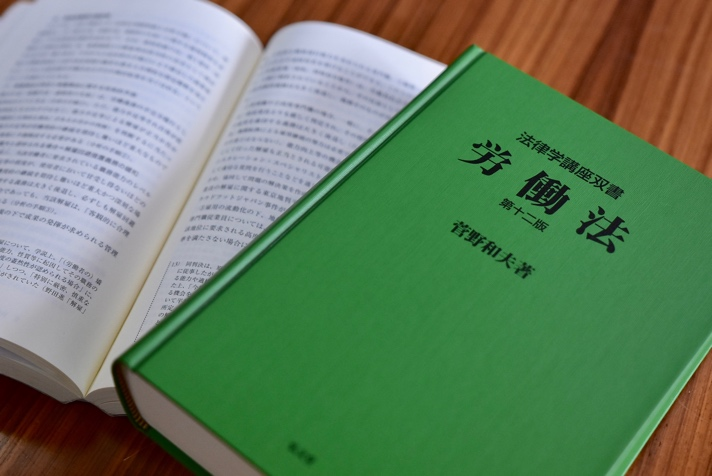第70回は、日本産業パートナーズ事件【東京高裁令5.11.30労働判例2024.9.15】です。
本件では、競業避止義務違反を理由とした退職金の減額処分の有効性が争われました。
1 事案の概要
Xさんは、平成24年から、投資組合の財産管理等を目的とする日本産業パートナーズ株式会社(以下「Y社」といいます。)に勤務していました。
XさんとY社との雇用契約書には、「Y社退職後1年間は、Y社と類似の会社への転職は行わないことに同意する。」という競業避止義務条項がありましたが、Xさんは、自身が関与していた投資先情報の資料を大量に印刷し、一部を持ち出したうえで、令和2年1月31日をもって退職し、同年2月からY社と競業関係にある投資事業を行うZ社に勤務しました(以下「本件競業避止義務違反行為」といいます。)。
Y社は、本件競業避止義務違反行為を理由として、就業規則により算出されたXさんの退職金704万円から525万円を減額して、179万円の退職金のみを支払いました。
そうしたところ、Xさんは、これを不服として訴訟提起しました。
第1審の東京地裁(令和5.5.19労働判例2024.9.15)は、Xさんの請求を棄却しましたが、Xさんはこれを不服とし、東京高裁に控訴を申し立てました。
2 競業避止義務条項の有効性
労働者は、労働契約の存続中は、信義則上当然に競業避止義務を負っていると解されているところ、労働契約の終了後については、労働契約書等において定めのある場合に限り、競業避止義務を負うことになると解されています。
もっとも、労働契約書等において定めのある場合であっても、労働者の職業選択の自由(憲法22条)の関係で無制限に競業避止義務を課すことはできません。
この点について、代表的な裁判例は、競業の制限が合理的範囲を超え、退職労働者の職業選択の自由を不当に拘束する場合は、その制限は公序良俗に反し無効になるとしたうえで、合理的範囲の確定にあたっては、①競業避止義務の期間、②場所的範囲、③制限職種の範囲、④代償の有無等をもとに判断するとしています(奈良地裁昭和45.10.23判時624号78頁)。
3 本判決の概要
控訴審も、以下のとおり判事して、Xさんの請求を棄却しました。
(1)本件競業避止義務の期間、範囲について
本件競業避止義務は、期間としては1年にとどまっているものである。
また、競業の範囲については、必ずしも明確にはされていないが、Xさんが退職を希望した際にY社から告知された範囲(カーブアウト等のバイアウト投資)を対象とするものと捉えれば、本件競業避止義務の範囲も不当に広範なものであるとまでは言えない。
(2)Xの地位は低かったという主張について
Xさんは必ずしも投資判断に関する決定権を有しているような地位にはなかったが、Y社内においては投資検討先の情報を自由に認識、取得することができたことからすると、比較的低い役職にある者も含めて競業避止義務の対象とすることには合理的な理由がある。
(3)代償の有無等
Y社がXさんに対して競業避止義務を課すことの代償として、平均1200万円を超える相当額の基本年俸を支払っている点については、必ずしも十分な代償措置であるとまでは言えないが、上記(1)及び(2)も踏まえると、本件競業避止規定が不合理なものであるとまでは言えない。
4 おわりに
今回もお目通しいただき、ありがとうございました。
終身雇用性が揺らぎ、転職が身近なものになっている昨今、競業避止義務違反、秘密保持義務違反のリスクは今まで以上に高くなっているものと存じます。顧問先の皆様におかれましては、退職時の取り扱いを含め、お気軽にご相談をいただけましたら幸いです。

弁護士 白石 義拓(しらいし よしひろ)
第二東京弁護士会所属。
2022年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。栃木県出身。