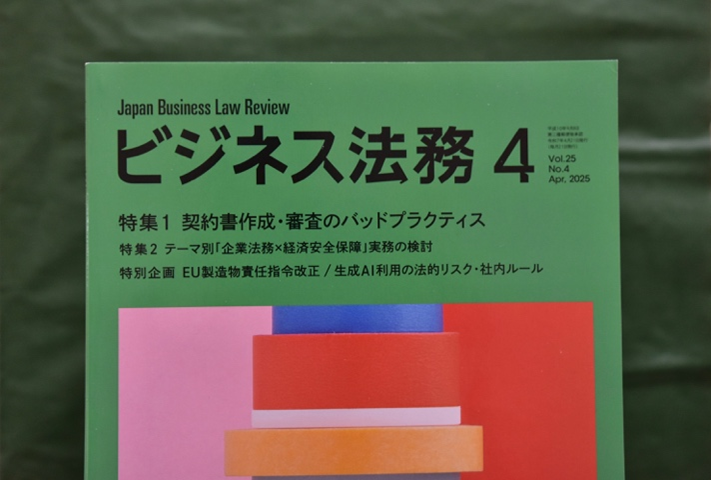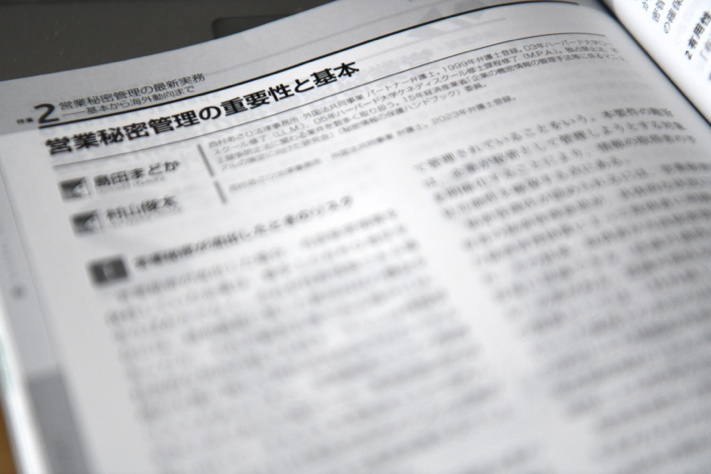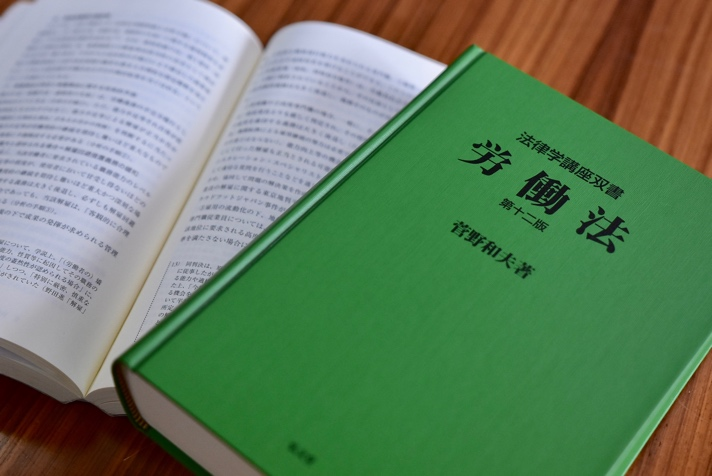『ビジネス法務』2025年4月号のTrend Eyeは「採用代行・退職代行サービスの法的留意点」(執筆:石居茜弁護士)です。採用代行や退職代行に関して職安法や弁護士法との関係について解説があります。
- ・採用代行とは
- ・委託募集の許可
- ・職業紹介とは
- ・採用代行が違法となる場合とは
- ・退職代行の法的問題点
<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>
1 採用代行について
採用代行とは、企業などの採用活動の全部又は一部を外部業者に委託するいわゆる採用支援サービスを利用することをいいます。
しかしながら、「労働者の募集」を第三者に報酬を与えて委託する場合には、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の許可を受ける必要があります。また、報酬の額についても、あらかじめ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の認可を受けなければならないといった法的な規制があります(報酬を与えない場合でも、厚生労働大臣又は都道府県労働局長への届出が必要となります。)。
委託募集の許可基準としては、募集主、募集受託者がそれぞれ職業安定法その他の労働関係法令に係る重大な違反がないこと、募集に係る労働条件が適正であること、募集に係る業務内容、労働条件が明示されていることなどが必要になります。
もっとも、許可を受けても委託された業者が面接などを行うことはできないとされています。
2 採用代行の法的留意点
上記の通り、採用代行として「労働者の募集」を外部に委託する場合、委託する会社が、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の許可を受けなければ違法となります。
しかしながら、募集、面接、選考、採否決定は自社で行い、求人広告の作成、採用試験や適性検査等の作成・実施・結果のまとめ・報告等を外部に委託するだけであれば、事業主以外の第三者が募集・選考したとまではいえず、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の許可は必要ないことになります。
また、許可を受けている職業紹介事業者に労働者の募集を委託する場合には、職業紹介事業者が求職者を募り、求職者を紹介することは「職業紹介」の範囲内といえますので、別途、自社が労働者募集の外部委託の許可を取得する必要はないことになります。なお、職業紹介はあくまで紹介ですので、採用内定まで委託することはできません。
3 退職代行の法的問題点
一方で、近年、従業員が退職する際に、退職代行サービスを利用するケースが増えています。この退職代行にも、法的な規制がありますので、退職代行を利用する場合には注意が必要です。
退職の意思表示というのは、労働契約の終了という法的効果を生ずる法律行為に該当します。
弁護士法第72条では、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁じており、罰則もあります。
退職代行業者が、退職の意思表示を代理して行うことは、法律行為を代理して行うことにほかならないため、弁護士法第72条に抵触し、法律違反とされてしまいます。残業代の請求やその他の交渉に関しても同様です。
もっとも、退職代行業者に弁護士がついているのであれば、弁護士が意思表示の代理や交渉を行うことで、弁護士法第72条違反の問題はなくなります。
退職代行業者で弁護士を利用できないという場合は、退職届の提出などは本人に書いて会社宛に郵送してもらうなど徹底する必要がありますのでご注意ください。
4 おわりに
いかがでしたでしょうか。今回は近年よく耳にする退職代行と、それと対照的な採用代行の法的留意点について紹介させていただきました。
自らの行為が気づくことなく法律違反となってしまうケースも少なくありません。法律に違反しているのでは?と少しでも気になることがありましたら、ぜひ一度弁護士までご相談ください。

弁護士 髙木 陽平(たかぎ ようへい)
札幌弁護士会所属。
2022年弁護士登録。2022年PLAZA総合法律事務所入所。北海道出身。

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)