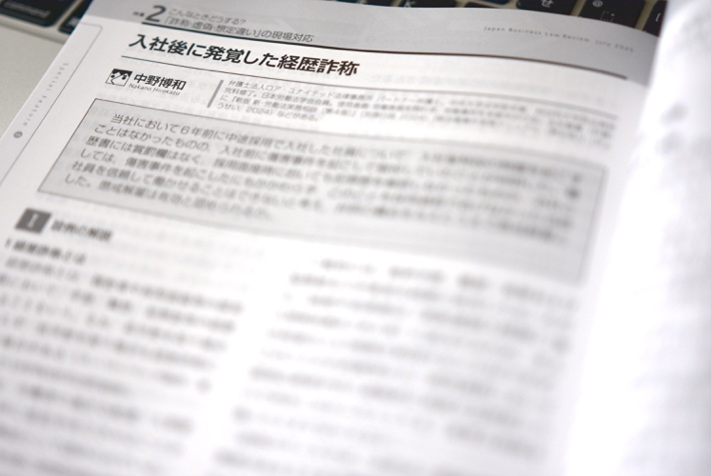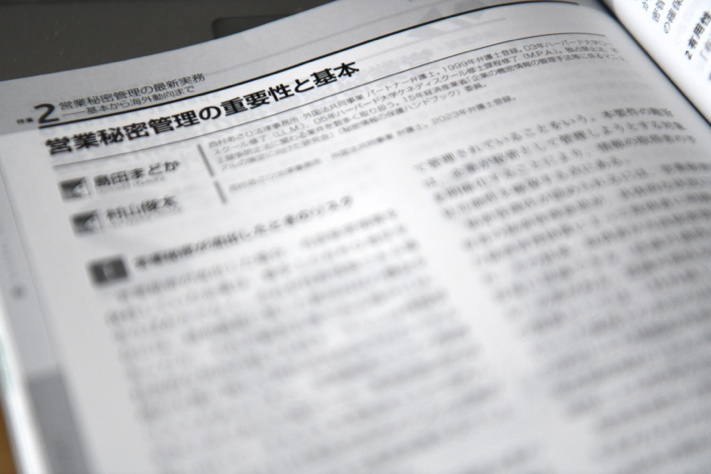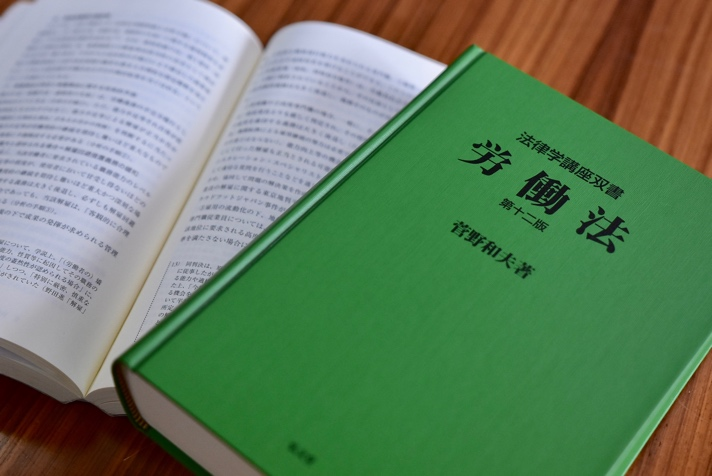『ビジネス法務』2025年7月号の「特集2」は「詐称・虚偽・想定違いの現場対応」です。この中で「入社後に発覚した経歴詐称」(執筆:中野博和弁護士)があります。中途採用で入社した社員が、過去に傷害事件を起こして服役していたことが判明。弁明の機会を与えたうえで懲戒解雇とした。この懲戒解雇は有効と認められるのか。解説があります。
- Ⅰ 設例の解説
- 1経歴詐称とは
- 2経歴詐称での懲戒解雇の有効性
- Ⅱ 教訓・対策
- 1要配慮個人情報
- 2中途採用
- 3入社後一定期間経過後の解雇
<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>
1 はじめに
本稿では、入社後に犯罪歴が発覚した社員を、経歴詐称を理由として懲戒解雇できるのかという問題点について解説されています。(元執筆者:中野博和弁護士)。
2 経歴詐称とは
経歴詐称とは、履歴書や採用面接等の採用過程において、学歴、職歴、犯罪歴等の経歴を偽ることをいいます。
この点、高学歴を装う場合だけではなく、低学歴を装う場合も経歴詐称に該当すると判断されることもあります(東京地判S55.2.15労判335号23頁)。
3 経歴詐称と懲戒事由
経歴詐称は、労働者の適正な配置、人事管理等の企業秩序に混乱を生じさせることから、一般に懲戒事由として認められています。
経歴詐称を理由として懲戒解雇をすることができるのは、その経歴詐称が事前に発覚していれば使用者は雇用契約を締結しなかったであろうと客観的に認められるほどの重要な経歴について詐称している場合に限られます(大阪高判S37.5.14民集13巻3号618頁)。
一般的には、最終学歴、職歴、病歴及び犯罪歴などは重要な経歴に該当しうるものとされています。
もっとも、病歴や犯罪歴は、「要配慮個人情報」(個人情報保護法2条3項)に該当するため、本人の同意なしに情報を取得することはできないものとされており、このこととの均衡から、採用過程において応募者自らが積極的に病歴や犯罪歴を申告しなかったとしても、重要な経歴を偽ったとまでは言えないと考えられています。
4 採用時の対策
そのため、経歴詐称入社を防ぐためには、採用過程において、病歴や犯罪歴などを業務能力などに関連させて質問をしておくことが重要です。
もちろん、病歴や犯罪歴は、「要配慮個人情報」に該当し、本人の同意なく情報を取得することはできないので、採用応募者は回答を拒否することもできます。
もっともこの場合、使用者は、その回答態様も考慮して、採用の可否を判断することにより一定の手立てをとることが可能です。
5 おわりに
今回もお目通しをいただき、ありがとうございました。
顧問先の会社様からも、経歴詐称が発覚したので懲戒解雇をすることは可能でしょうか。というご質問をいただくことはままございます。本稿をきっかけとして、経歴詐称の発覚に対する事後対応のみならず、経歴詐称の未然防止にも努めていただけましたら幸いです。

弁護士 白石 義拓(しらいし よしひろ)
第二東京弁護士会所属。
2022年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。栃木県出身。

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)