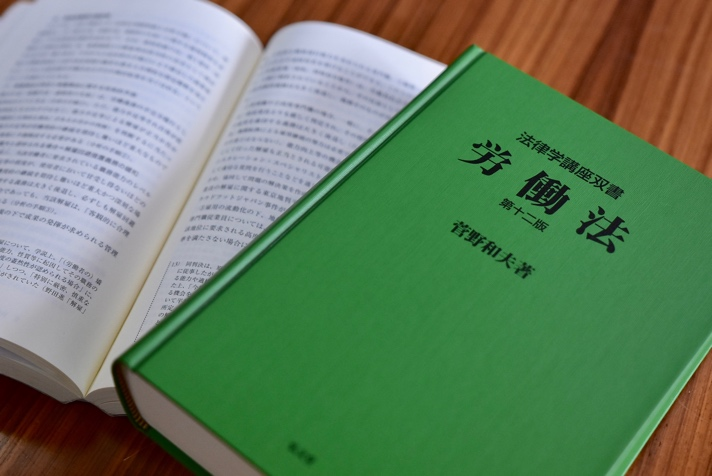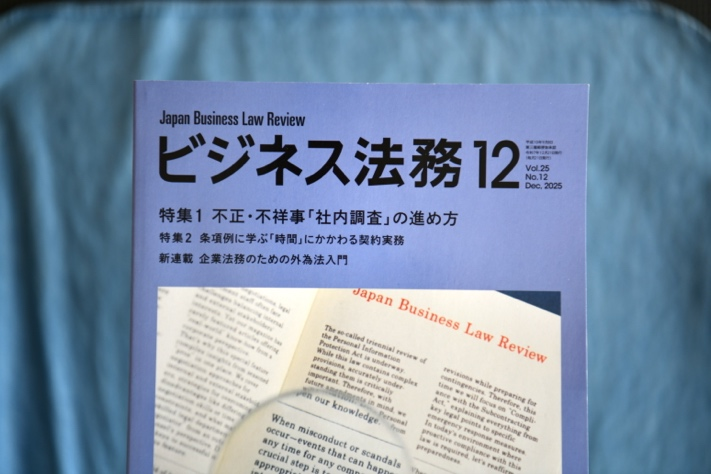第66回目は「司法書士法人はたの法務事務所事件」(東京高裁 令5.3.23判決)です。
1 事件の概要
本事件は、司法書士法人はたの法務事務所で勤務していた従業員のXさんが、はたの法務事務所(以下「Y事務所」)に対して、平成30年6月7日以降、Y事務所から就労を拒否され、賃金が未払いになっているとして、平成30年6月7日以降の賃金を請求した事件です。
Xさんは、平成30年6月7日以降、Y事務所で就労していませんでしたが、雇用契約が継続しているにもかかわらず、Y事務所が一方的に就労を拒否していた場合、Xさんは就労しなくても、賃金を請求することができます(民法536条2項)。
これに対し、Y事務所は、Xさんの訴えに対し、XさんとY事務所との雇用契約は、契約当初から有期の契約であり、契約期間が満了しており、雇用契約は終了したとして、賃金の支払い義務はない旨主張しました。
証拠上、XさんとY事務所の雇用契約書には、雇用期間を1ヶ月の有期とする記載があり、一方で、Xさんが応募した求人サイトの募集要項には雇用形態を「正社員」(一般的に無期な場合が多い。)とする記載がありました。
そこで、本裁判では、XさんとY事務所との雇用契約が有期の契約であったか無期の契約であったかが争われました。
2 裁判所の判断
裁判所は、まず、Xさんの応募した募集要項には雇用形態を「正社員」とする記載があり、契約期間については特段、何の記載もなかったことを理由に、募集要項は無期契約を前提としていると判断しました。
そして、XさんとY事務所との、採用前の面接においては、契約期間について何ら説明がなく、Y事務所はそのままXさんを採用することに決めており、XさんとY事務所との雇用契約は、募集要項の記載の通り、期間の定めのないものとして(無期として)成立したと認定しました。
一方で、雇用契約書には、契約期間を1ヶ月間とする有期の定めがあり、Xさんの署名押印もありましたが、1ヶ月後の契約期間満了日より前に労働契約の更新について面談等で話し合われたことがないこと、契約期間満了日以降もXさんがY事務所でそのまま勤務を継続していること、雇用契約書に署名押印したのは、勤務を開始してから1ヶ月以上も後であること、ひとたび勤務を開始すれば労働者が使用者からの不利益な取り扱いを恐れ萎縮して適切な意思表示ができないこともあり得ること、Y事務所はXさんに執拗に退出届の提出を求めており、有期の契約であると確定的に認識していたのであれば、退職届の提出を執拗に求める必要がないことなどを摘示して、雇用契約書の記載が、雇用契約が無期であったことの認定を覆すに足りるものではないと判断しました。
3 結語
いかがでしたでしょうか。今回は、雇用契約の契約期間が有期か無期かが争われた事件を紹介させていただきました。募集要項では無期の契約であり、契約書では有期の契約であった場合にどのような判断がなされるのか、非常に興味深い内容の裁判でした。
ご留意していただきたいのは、募集要項と契約書を比較して、常に募集要項が優先されるというわけではないことです。
上記の通り、面接の内容・従前の説明や話し合い・就労停止時の状況など、裁判所における考慮事項は多岐に渡ります。
本事件のようなトラブルにならないよう、雇用契約を締結する際は、雇用期間についての十分な説明や適切な時期の契約書類の取り交わしが必要といえます。仮に、本事件のように募集要項と契約内容が異なる場合には、契約期間についての同意書の取り交わしや採用面接時の協議内容を記録として残しておくことが有用です。
本裁判例を、健全な労使関係の構築にお役立ていただけますと幸いです。

弁護士 髙木 陽平(たかぎ ようへい)
札幌弁護士会所属。
2022年弁護士登録。2022年PLAZA総合法律事務所入所。北海道出身。