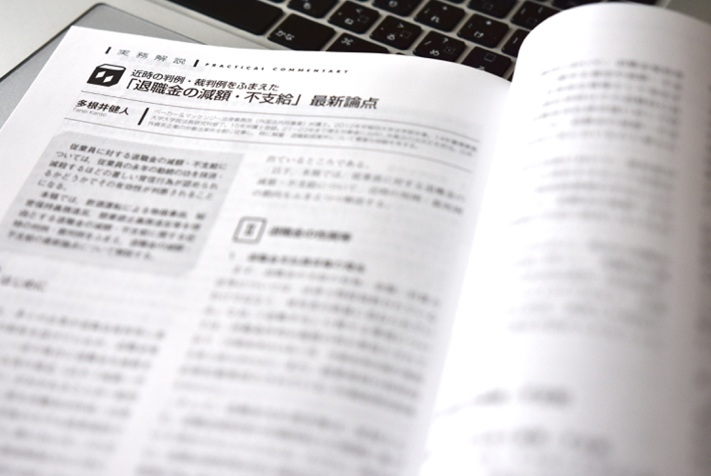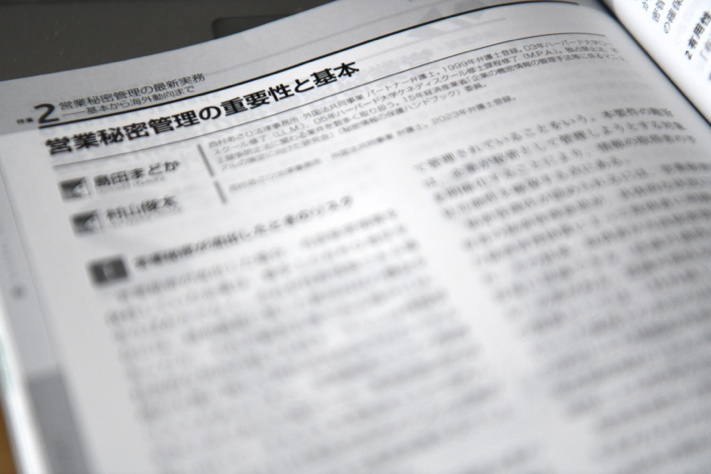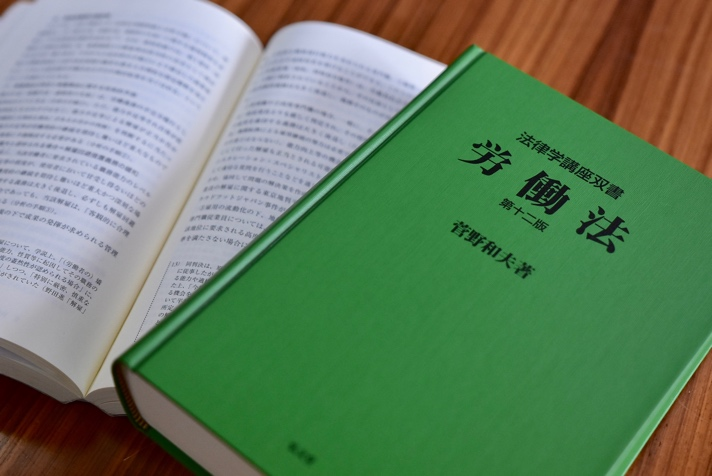『ビジネス法務』2025年4月号の「実務解説」は「『退職金の減額・不支給』最新論点」(執筆:多根井健人弁護士)です。本稿では、飲酒運転による物損事故、秘密保持義務違反などを理由とする退職金の減額・不支給に関する近時の判決・裁判例をふまえ、最新論点について解説しています。
- Ⅰ はじめに
- Ⅱ 退職金の性質等
- 1 退職金支払請求権の発生
- 2 減額・不支給条項自体の有効性
- Ⅲ 退職金の減額・不支給
- 1 退職金の法的性格と減額・不支給
- 2 退職金の減額・不支給の有効性
- 3 退職後に判明した事由に基づく退職金の減額・不支給と退職金返還請求
- Ⅳ 近時の判例・裁判例
- 1 飲酒運転による物損事故
- 2 秘密保持義務違反
- 3 競業避止義務違反
- 4 業務引継ぎの懈怠
- Ⅴ おわりに
<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>
1 はじめに
本稿では、従業員が不祥事を起こして退職した場合に退職金を不支給・減額する旨を定めた規定(以下「退職金不支給規定」)の有効性について、近時の裁判例をふまえて解説されています。
2 退職金の性質・退職金不支給規定の有効性
退職金請求権は、就業規則等の労働契約上の規定を根拠として発生するもので、その性質は、①賃金の後払い的性質(雇用期間中の労務提供に対する対価の事後的精算)、②功労報酬的性質(従業員の永年の勤続に対するご褒美)という2つの性質から成り立っていると一般的に説明されています。
退職金不支給規定の有効性を検討するうえでは、この①、②いずれの性質が強い規定であるのかも考慮しながら、その有効性を判断する必要があります。
3 退職金不支給規定の有効性に関する裁判例
・飲酒運転による物損事故
市役所の職員が、大量飲酒をした後に2度の自動車物損事故を起こし、事故直後の捜査に対しても虚偽の説明をするなどしていた事案において、裁判所は、住民の公務に対する信頼を著しく失墜させたと評価して、退職金全部不支給処分を有効と判断しました。(大津市懲戒免職処分事件:最判令和6年6月27日労経速2558号3頁)
・秘密保持義務違反
転職に際して社内システム上のデータファイルを持ち出した事案において、裁判所は、従業員の勤続年数が5年と短期であったことも考慮して、退職金全部不支給処分を有効と判断しました。(伊藤忠商事事件:最判令和4年12月26日労経速2513号3頁)
・業務引継ぎの懈怠
他方、自己都合で退職した従業員に対する業務引継ぎ懈怠を理由とする退職金不支給事案において、裁判所は、勤労の功を抹消してしまうほどの著しい背信行為があったとまでは評価できないとして、退職金支払い請求を認めました。(東京地裁令和元年9月27日労経速2409号13頁)
4 おわりに
今回もお目通しをいただき、ありがとうございました。
終身雇用制が揺らぎ、転職が珍しいことではなくなった昨今、退職金を受け取るという場面は一度限りのことではないかもしれません。裁判例をいくつかご紹介させていただきましたが、退職金不支給規定の有効性については、事案固有の判断が必要になってきますので、顧問先の皆様におかれましては、お気軽にご相談をいただければと存じます。

弁護士 白石 義拓(しらいし よしひろ)
第二東京弁護士会所属。
2022年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。栃木県出身。

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)