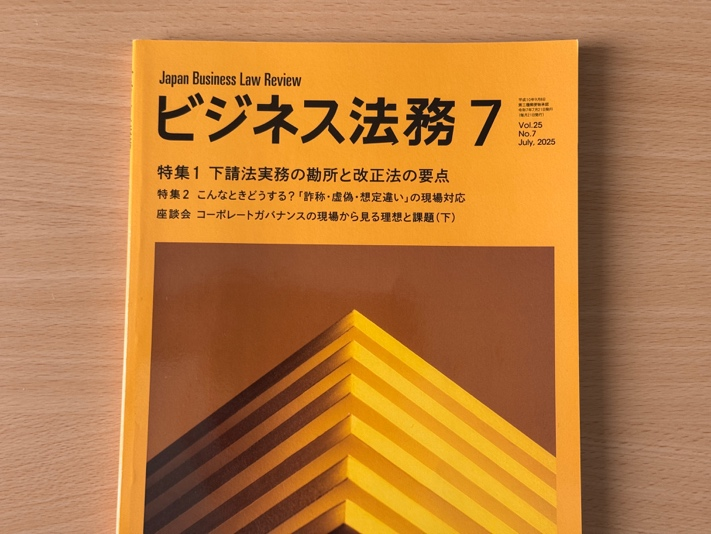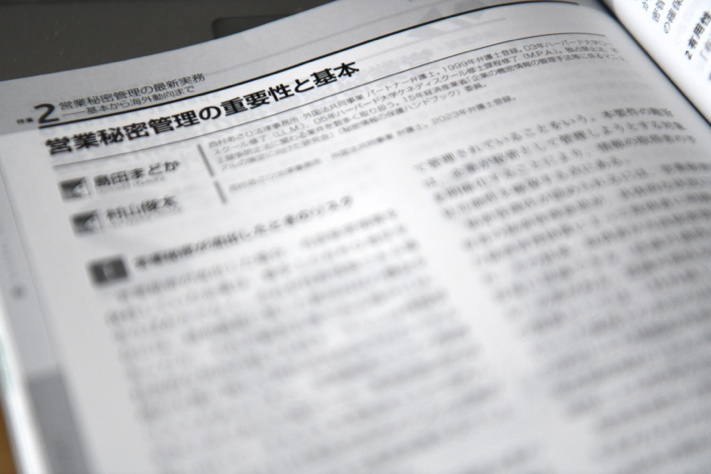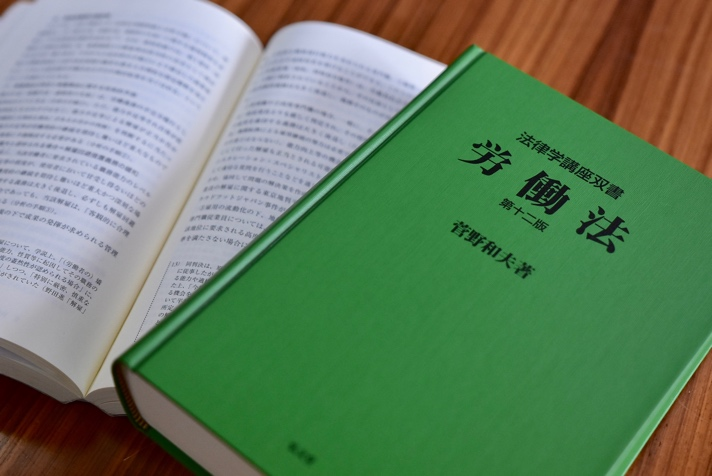『ビジネス法務』2025年7月号の「特集1」は「下請法実務の勘所と改正法の要点」です。この中で「基礎知識の再点検」(執筆:森悠樹弁護士)があります。実務上は重要な下請法の基礎知識についてQAを交えながら紹介し、下請法規制の勘所が解説されています。
- (1)法の適用範囲
- Ⅰ はじめに
- 1下請法ってどんな法律?
- 2下請法の勘所
- Ⅱ 下請法の適用範囲
- 1適用範囲
- 2委託取引要件
- 3資本金要件
- (2)親事業者の義務と禁止行為
- Ⅰ 親事業者の義務
- 1親事業者の義務の概要
- 2いわゆる3条書面の交付義務
- 3支払期日を定める義務
- 4いわゆる5条書類の作成・保存義務
- 5遅延利息の支払義務
- Ⅱ 親事業者の禁止事項
- 111の禁止行為の概要
- 2支払遅延
- 3代金減額
- 4買いたたき
<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>
1 はじめに
本稿では、下請法の適用範囲、親事業者の義務と禁止行為などの基礎知識について解説されています。
2 下請法とは
下請法は、下請取引の公正化および下請事業者の利益保護を目的とする法律です。下請法は発注者(親事業者)に4つの義務を課すとともに、11の類型の行為を禁止しています。
下請法に違反した場合の最大のリスクは、勧告(7条)となっています。
3 下請法の適用範囲
下請法の適用範囲は、①委託取引の内容(委託取引要件)、②資本金の区分(資本金要件)により、形式的・機械的に決まります。
下請法の適用範囲となる委託取引は、①製造委託、②修理委託、③情報成果物作成委託、④役務提供委託、の4類型があります。
資本金要件は、委託取引の類型に応じて金額基準が定められています。
4 親事業者の義務と禁止行為
親事業者が負う義務は、①書面の交付義務、②支払期日を定める義務、③書面の作成・保存義務、④遅延利息の支払義務の4つです。
①は、製造委託等をした場合は、直ちに、委託内容、下請代金等を記載した書面を下請事業者に交付しなければならないというものです。
②は、下請代金の支払期日を受領日後60日以内かつできるだけ短い期間に定めなければならないというものです。
③は、下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存しなければならないというものです。
④は、支払いが遅延した場合は、受領日後60日経過後は、年14.6%の遅延利息を支払わなければならないというものです。
親事業者の11の禁止行為は、①受領拒否、②下請代金の支払遅延、③下請代金の減額、④返品、⑤買いたたき、⑥購入・利用強制、⑦報復措置、⑧有償支給原材料等の対価の早期決済、⑨割引困難な手形の交付、⑩不当な経済上の利益の提供要請、⑪不当な給付内容の変更および不当なやり直し、となっています。
5 おわりに
今回もお目通しをいただき、ありがとうございました。
顧問先の会社様から、契約書のリーガルチェックのご依頼を承ることは多くございます。契約書のリーガルチェックでは、依頼者様に不利な条項がないか等の視点に加え、下請法などの強行法規違反がないかという視点も重要です。顧問先の皆様におかれましては、契約書に下請法の適用があるか、下請法違反の契約書となっていないかなど、お気軽にご相談をいただければと存じます。

弁護士 小川 頌平(おがわ しょうへい)
札幌弁護士会所属。
2025年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。北海道出身。

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)