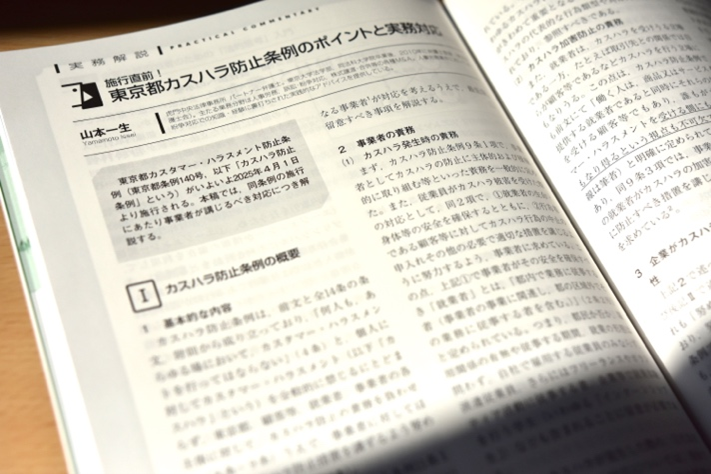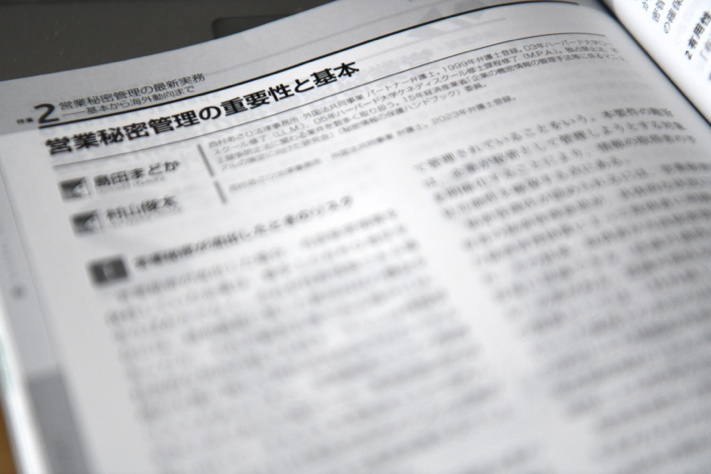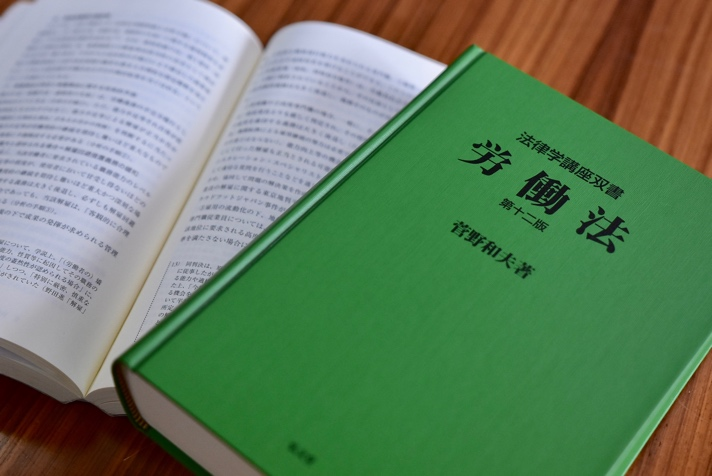『ビジネス法務』2025年5月号の「実務解説」は「東京都カスハラ防止条例のポイントと実務対応」(執筆:山本一生弁護士)です。東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が2025年4月1日から施行されました。この条例の施行にあたり事業者が講じるべき対応について解説があります。
- Ⅰ カスハラ防止条例の概要
- 1基本的な内容
- 2事業者の責務
- 3企業がカスハラ対策に取り組むべき必要性
- Ⅱ 企業が講ずべき措置
- 1概要
- 2平時から行うべき準備
- 3有事での対応
- Ⅲ おわりに
<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>
本記事では令和7年4月1日に施行された東京都カスハラ防止条例のポイントと実務対応についての解説がなされています。北海道においても令和7年4月1日に北海道カスハラ防止条例が制定された他、安全配慮義務の観点からも、事業者が適切なカスタマーハラスメント対応を行わなかった場合、従業員から損害賠償請求がなされるリスク(横浜地裁川崎支部令和3年11月30日判決、東京地裁平成30年11月2日判決)があるため、本記事記載の実務対応はカスタマーハラスメントに対する社内体制の整備に当たって参考になると思います。
東京都カスハラ防止条例の大まかな内容としては、個人によるカスタマーハラスメントの全般的な禁止(第4条)、事業者に対するカスタマーハラスメント防止措置の構築の努力義務(第14条)です(なお、罰則はありません。)。
事業者が講ずべき取組について、まず、平時の対応として、カスタマーハラスメントに対する基本方針の策定と従業員への周知・啓発、被害者のための相談対応体制の整備(相談窓口の設置、適切な相談対応の実施等)、有事における対応方法や手順の作成(現場での初期対応の方法や手順の作成、報告・相談・指示・助言の方法や手順の作成)、社内での教育・研修の実施が挙げられます。次に、有事の対応として、事実関係の正確な確認と事案への対応、被害者の安全確保と精神面・身体面の配慮、再発防止のための取組の策定等が挙げられます。
本記事では、上記の実務対応について、より具体的な取組内容が記載されています。この機会に是非ご一読ください。

弁護士 小熊 克暢(おぐま かつのぶ)
札幌弁護士会所属。
2020年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。北海道出身。

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)