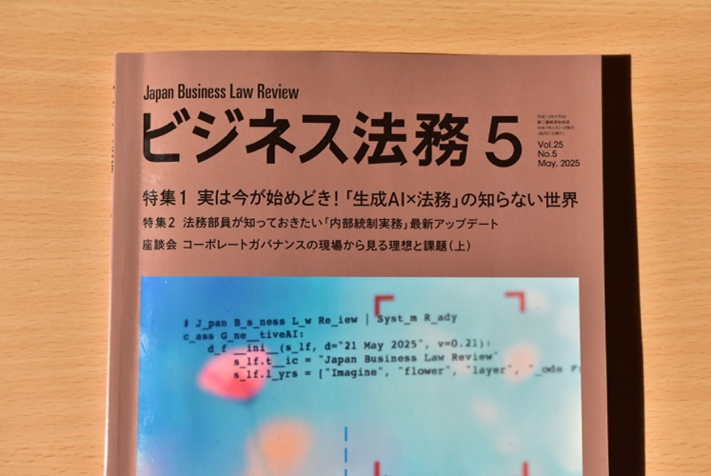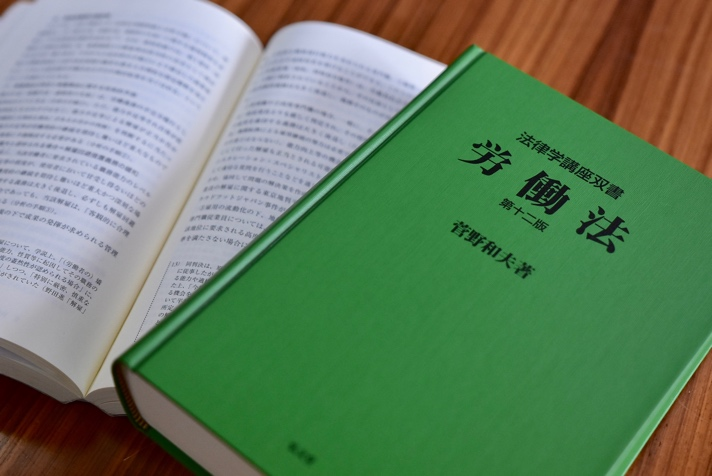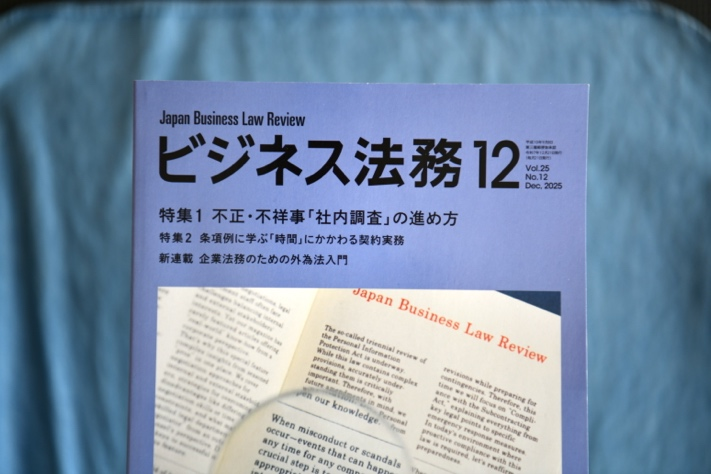『ビジネス法務』2025年5月号の「特集1」は「『生成AI×法務』の知らない世界」です。この中で「何から始める?生成AIの法務活用」(執筆:金子晋輔弁護士)があります。筆者が2年間の試行錯誤から見えてきた、シンプルで実践的な活用術が紹介されています。
- ・3つの視点と3つの準備の対応関係
- ・仮想ケーススタディ:CK製作所の場合
- ・ケーススタディから見えてくるポイント
<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>
1 はじめに
近年、ChatGPTなどといった生成AIの進歩が目覚ましく、2025年は生成AI本格普及の年と言われています。生成AIを自社に導入し、業務効率化を図ろうとする会社も増えてきています。AIの導入により、業務の効率化にとどまらず、社員の能力拡張、事業・業務全体の変革、生産性向上、収益性向上など様々な利益を享受することが期待されますが、一方で、著作権侵害などの法的なリスクもあるとされており、AIの導入に慎重になっている会社も少なくありません。
2 本記事について
本記事では、会社がAIを導入するにあたり、「何から始めればいのか?」を考えるヒントとして、「3つの視点と3つの準備」というフレームワークが紹介されています。仮想のケーススタディを題材に、このフレームワークを当てはめ、生成AIの法務活用推進の基盤を理解することができます。
仮想のケーススタディとしては、工作機械や産業ロボットを手がけるとある製作所が、法務部門でのAI活用に悩んでいるというものでした。
①経営の視点として、常務取締役においては、競業他社がAIを活用した新サービスを展開し始めており、自社の市場における成長を確実なものとするため、自社の法務のデジタル化を加速させたいが、法務の質も落とさないよう両立させたいという課題に直面していました。
常務取締役は、まずは、「情報管理の準備」として、情報システム部門と法務部門の合同チームを立ち上げ、情報の区分けから始めました。AIを導入するにあたり、「AI活用可能」、「要判断」、「活用禁止」という情報の区分けをすることで、各部門に、AIで何ができるのかを示し、安心してAIを活用できる土台を作りました。
②現場の視点として、法務課の主任は、課内で年間3000件の契約審査を行っており、最近は海外案件も増え、既存のテンプレートでは対応しきれなくなっており、AIの助けが必要だが、リスクも気になり安全にAIを活用したいという課題を感じていました。
法務課主任は、「段階的実証の準備」として、すぐにできることから始めることとし、最もリスクの低い業務である、法務ニュースの要約からAI活用を着手しました。この取り組みが好評だったため、次に、契約書の定型条項の解説作成、さらに、海外の一般的契約条項の収集と整理というようにAI活用の幅を徐々に広げていきました。
③発展の視点として、法務課の課長は、部下たちの残業が深刻な状況であることを危惧しており、一方で、法務部門が変わらなければ、全社の改革も進まないと痛感していました。
法務課長は、「推進体制の準備」として、まず1ヶ月のお試し期間を設定しました。課員全員がAIツールを実際に使ってみてよかった点も悪かった点も率直に共有することとしました。その結果を活用事例集としてまとめ、具体的な使い方と注意点を示しました。また毎週金曜日をAI活用TIPs共有会の日とし、15分程度でノウハウを共有する仕組みも作りました。
3 おわりに
いかがでしたでしょうか。今回は、生成AIを導入するための準備のフレームワークについて紹介させていただきました。生成AIの導入には、完璧な準備を目指すのではなく、できることから始めるというマインドが重要だとも言えるでしょう。本記事をぜひ一度お目通しいただけますと幸いです。

弁護士 髙木 陽平(たかぎ ようへい)
札幌弁護士会所属。
2022年弁護士登録。2022年PLAZA総合法律事務所入所。北海道出身。

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)