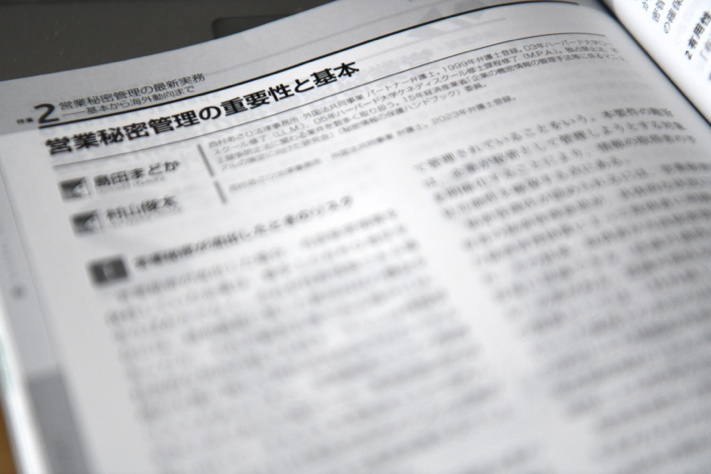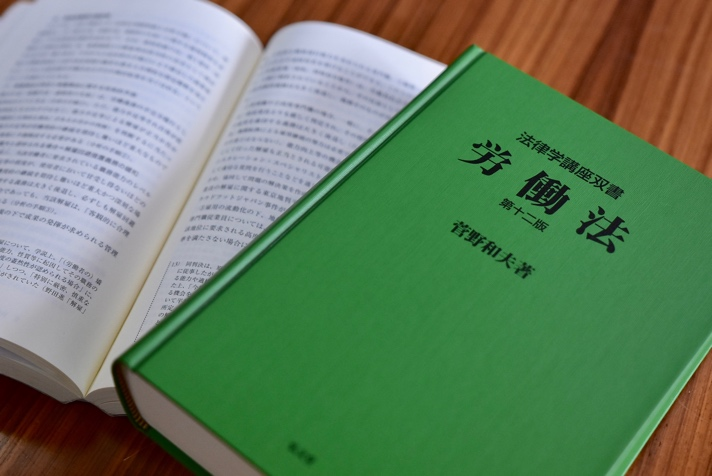第49回は東京三協信用金庫事件(東京地判令和4年4月28日労判1291号45頁)です。
パワーハラスメントの加害者に対する降格処分の有効性が争われた事案です。パワーハラスメントの定義については、労働法の基礎第49回をご確認ください。
まず、事案の概要について、XさんはY社の管理職に就いていました。Xさんは、Y社の一職員であり、Xさんとは異なる部署に所属しているAさんに対し、次のような発言をしました(以下、「本件各発言」といいます。)。
①(Aさんによる、Y社の新勤怠管理システムの初期ID、PWのメール送付行為について、Aさんに何らの落ち度もないにもかかわらず、)不適切な方法で勝手にID、PWをメール送信したなどと強い口調で詰問した(発言①)。
②(発言①に続けて、)ただでさえ周りから受け入れられていないのに勝手なことをしている、あなたが勝手なことをしていると皆が発言している、等と指摘した(発言②)。
③(発言①、②に続けて、)Aさんの他の従業員に対する態度が気に入らない、等と発言した(発言③)。
Aさんは、Xさんからの上記の発言等を受けて、適応障害を患い、最終的にY社を退職しました。Y社は、懲戒委員会を複数回開催してXさんに弁明の機会を設けた上で、Xさんの本件各発言がパワーハラスメントに該当し、Y社就業規則の懲戒事由に該当するとして、Xさんを降格処分(以下、「本件降格処分」といいます。)としました。これに対し、Xさんは、本件降格処分の有効性を争いました。なお、Xさんは、過去に、Y社からけん責の懲戒処分や10日間の出勤停止等の懲戒処分を受けていました。
裁判所は、本件各発言のパワーハラスメント該当性について、以下のように判断しました。
まず、発言①について、Aさんの行動について、Xさんから注意・叱責を受けるような落ち度はない。また、Aさんは、Xさんとは異なる部署の従業員であるところ、Aさんに注意ないし指導を行うのであれば、組織管理上、Aさんを管理監督しているAさんの部長に対して報告や指導の促しを行うべきである。そもそも、AさんはAさんの部長の了解のもとにメール送信を行っている。そのため、発言①は、何らの根拠もないままにAさんの業務遂行が不適切であると決めつけて一方的に非難するものというほかない。
また、発言②について、発言①のメール送付行為の当否とは関連しない事柄であり、業務上の注意、指導としての発言であるとは言えない。むしろ、XさんのAさんに対する悪感情を他の職員の総体的な意見であるかのように置き換えて、Aさんの人格を否定するものであり、極めて悪質である。
そして、発言③についても、発言①のメール送付行為とは無関係の事柄であり、内容も、業務上の指導というよりも、Aさんに対する悪感情を述べたものと言わざるを得ない。
よって、本件各発言は、管理職という優越的地位にあるXさんが、他部署の一職員であるAさんに対し(優越的な関係を背景とした言動)、一方的かつ高圧的に理由なく業務作業を非難するもの(業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの)であり、Aさんに強度の心理的負荷を与えたもの(労働者に精神的な苦痛を与えること、労働者の就業環境が害されるもの)と評価すべきである。本件各発言はY社就業規則等におけるパワーハラスメントに該当し、懲戒事由に該当する。
その上で、本件降格処分の有効性(客観的合理的理由の有無、社会通念上の相当性の有無)について、a.本件各発言がその目的、態様ともに悪質であるといえること、b.発言に至る経緯や動機に酌むべき事情が見受けられないこと、c.Aさんに重大な損害を被らせたものであること、d.Y社の組織秩序に対する影響も軽視できないこと、e.Xさんのパワーハラスメントの防止に対する規範意識の低下も窺われること、f.懲戒処分の手続面の相当性もあること等を踏まえ、社会通念上の相当なものである。よって、裁判所は、本件降格処分は有効である、と判断しました。
本判決は、パワーハラスメントに対する事業者側の対応を検討するにあたって、参考となる事例であるといえます。

弁護士 小熊 克暢(おぐま かつのぶ)
札幌弁護士会所属。
2020年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。北海道出身。